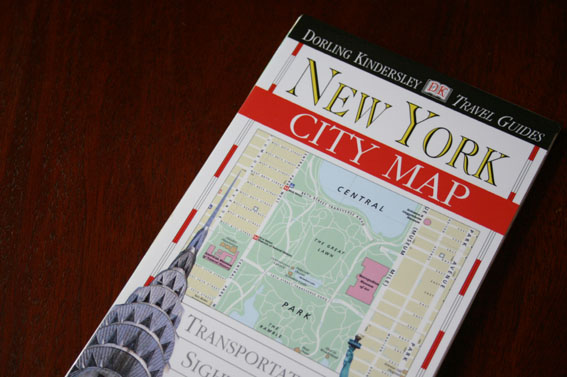ニューヨークからバンガロアに到着した深夜、ドライヴァーのクマールが迎えに来てくれるはずだった。しかし、空港に現れたのは、別のドライヴァーだった。
わたしたちは、まだ車を購入していない。地元のカーサーヴィスの会社から、月契約で自動車とドライヴァーを借りている状態だ。
従ってはドライヴァーのクマールは、わたしたちが直接雇っているのではなく、カーサーヴィス会社の雇用者である。とはいえ、数カ月間、毎日のように我が家専門のドライヴァーとして来てくれており、家政夫モハンとも親しく、そこそこ気心のしれた間柄となっていた。
クマールは、他のドライヴァーに比べ、英語力が高いし、時事問題にも詳しく、知的な人物であった。一方、南インドのEasy Going な性質も色濃く、時間に曖昧な部分もあった。
彼はお金に困っていたようだ。
無論、この国でお金に困っていない人は、わずか数%に過ぎないだろう。彼はしかし、倹約家というわけでもないらしい。モハンよれば夫婦揃ってかなりの「酒飲み」であるとのこと。
それは、彼らにとって数少ない楽しみのひとつなのかもしれない。
さて、戻って来た翌日も、クマールは現れず、別のドライヴァーが来たので、不審に思った夫がカーサーヴィス会社に電話をした。マネージャーから事情を聞いたのち、電話を切った夫曰く。
「クマール、いなくなったんだってよ。僕達が旅に出た翌日、会社に来て、オートバイを買うから給料を前借りさせてくれって頼んだらしい。お金を受け取って、それきり会社に来なくなったんだって。携帯電話に連絡しても出ないらしい」
わたしたちが旅に出る1週間ほどまえ、彼は携帯電話を水の中に落としてダメにしてしまっていた。中古の電話を買いたいのだが、手持ちのお金がないから、2000ルピーを貸してくれないかと、わたしは彼に言われた。
いくら薄給とはいえ、わずか50ドルにも満たない金を、貯えていないわけではないだろう。
第一、彼は、わたしたちの、前述のとおり、直接の雇用者ではない。モハンとは別なのだ。
「貸すことはできない。」
わたしはきっぱりと応えた。それ以上に、不快感すら示した。はっきりとさせておかなければ、と思ったのだ。
彼がいなくなった、と聞いて、わたしはあのとき、貸さずによかったと思った。それはもちろん、2000ルピーが惜しいから、ではない。
「マダム、旅行先から、なんでもいいから、お土産を買って来てください」
クマールにそう頼まれていた。高いものではなく、でも、彼が喜びそうなものはなんだろうと考えた。
マンハッタンの土産物店で、ラミネート加工がなされたシティマップを買った。チョコレートや、キーホルダーなどよりは、ずっと気の利いたお土産に思えたのだ。
受け取り手のない地図は、わたしのものとなった。